

前回のブログでは、竹岡『東大要約』の「38 欧州での子どもの権利の変遷」では、「大規模産業」という意味不明な言葉を使っていることを指摘し、むしろ「産業化以前」あるいは「産業革命以前」といった用語にすべきだったことを論じました。また、竹岡の不適切な訳語の原因には、研究社の『英和大辞典』があるのではないかと述べました。
今回は、前回のブログの補足をします。というのは、竹岡の38章の解説文には、その訳語以外にもちょっと誤読をしていることに気が付いたからです。ちょっと細かい点のようにも見えますが、歴史認識の上で重要な論点を含むので、ここで簡単に指摘します。
解答に至る解説文の中にですが、以上のような要約文があります。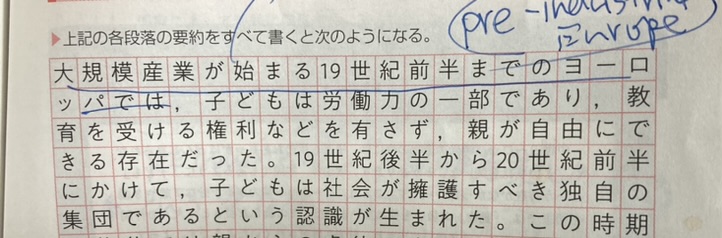
竹岡「大規模産業(⇛産業革命)が始まる19世紀前半までのヨーロッパでは、子どもは労働力の一部であり、教育を受ける権利などを有さず、親が自由にできる存在だった」と、本文の第一段落で要約しています。
ぼーっと読んでいるとなんの問題もありません。しかし世界史の常識と照らし合わせてみれば、この日本語にはちょっと不味いですね。
と言うのは、竹岡の要約文を読むと、(1)産業革命が19世紀前半に始まったかのように読めてしまうるからです。しかし産業革命が始まったのは、18世紀前半から中頃だと言われています。だから、これは要約文としては、ちょっと駄目なのです。
(2)竹岡の要約文を読むと、産業革命が始まると、時を待たずして子どもの権利が認められたかのように見えます。しかし、子どもの権利が認められ始められるようになったのが19世紀後半であるが、産業革命が始まったのは18世紀前半だとすれば、産業革命の開始後子どもの権利をなかなか認められなかったのだ。それも100年くらい、あるいはそれ以上の長期にわたって、子どもの権利はずっと無視されてきたのだと解釈できるはずなのです。
考えてみれば、我々は19世紀のイギリスの児童に対して強いてきた重労働の歴史を我々は知っているではありませんか。19世紀の著名なノンフィクションやフィクションーーエンゲルスやディケンズの著作がその代表となるでしょうーーは、今なお言及されています。
もっとも私は、要約文に深読み考察を書けと主張している訳ではありません。しかし、産業革命が起きたら、すぐにでも子どもの権利が認められるようになったかのような要約文は、誤解を与えるのでちょっと不味いだろうと指摘しているに過ぎません。ただし、誤解なきように付け加えると、模範解答の部分は問題ありません。不味いのは、途中の要約解説の箇所だけです。
なお、原文では以下の通りです。丁寧に読めば、「産業革命以後に」子供に対する味方が変化したと記述されているわけではないのです。
In pre-industrial Europe, child labour was a widespread phenomenon and a significant part of the economic system. Until and during the nineteenth century, children beyond six years of age were required to contribute to societies according to their abilities.